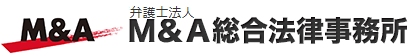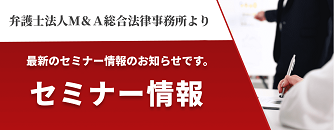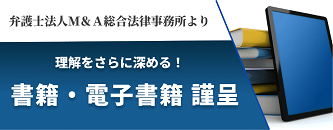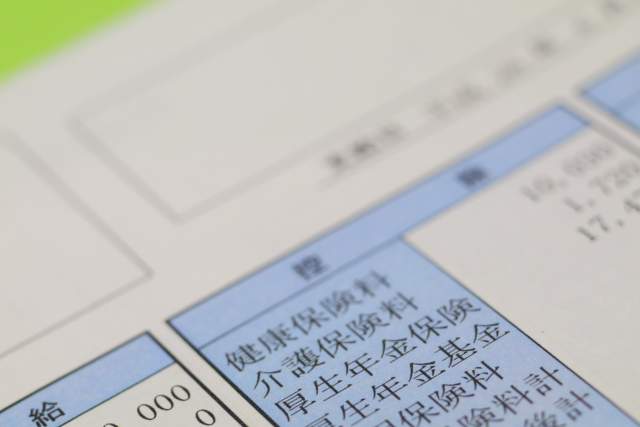職務発明対価を請求したい技術者様へ
自分が研究したものが特許になったことで会社が利益を上げている。
「発明報奨金」を会社に請求したいのだが、どうしたらよいのか。また、いくら請求できるのか?
職務発明の対価を請求訴訟が増えています。
職務発明とは?
職務発明とは、会社の従業員が業務を行った結果、発明がなされ、それについて特許を受ける権利を会社に譲渡した場合には、会社はその従業員に「相当の対価」を支払うことが必要とされており、これを職務発明対価といいます。
職務発明対価を請求したい技術者様へ
まず、「職務発明」に該当するかを確認することが必要です。特許法35条1項に定められている要件としては、①従業員等がなした発明であること、②使用者等の業務範囲に属する発明であること、③その発明をするに至った行為が、現在又は過去の職務に関すること、が必要です。
すなわち、特許法の原則からすると、特許を受ける権利は、職務発明であってもそうでなくても、発明した個人にあるのであり、職務発明の特許を受ける権利は、発明した従業員に存在するのです(特許権以外の商標権・著作権などの知的財産権は取扱が異なっています)。
しかし、就業規則等、会社との事前の契約において、その特許を受ける権利をあらかじめ会社に譲渡していることが多く存在します。
職務発明対価はいくらなのか?
これについては、平成16年の特許法が改正された前後(施行日は平成17年4月1日)によって異なります。
いわゆる、青色発光ダイオード裁判の結果に驚いた産業界が政府に働きかけをして、特許法が改正(改悪?)されたのです。その後、青色発光ダイオード裁判でも、発明者である中村教授が実質的に敗訴したため、日本の技術者の地位向上が大幅に遅れ、日本の技術大国も折り曲り地点を迎えました。
平成17年4月1日以前に会社に譲渡された職務発明
旧特許法35条4項では、職務発明対価を算定するため、①その発明により使用者等が受けるべき利益の額と、②その発明がされるについて使用者等が貢献した程度を総合考慮するものとされています。
平成17年4月1日以降に会社に譲渡された職務発明
平成17年4月1日以降に会社に譲渡された職務発明については、現行特許法35条4項及び35条5項が適用されます。
すなわち、職務発明対価を算定するため、まず、①就業規則等において対価の定めがある場合は、その策定に際して行う協議の状況、策定された基準の開示状況、算定についての意見聴取の状況等を考慮し、②社内規定に基づき算出された職務発明対価の定めが合理的な場合はそれによるとして、社内規定の内容が尊重されることとなりました。
ただ、一応、③職務発明対価に関する社内規定がない、または職務発明対価に関する社内規定の内容が不合理な場合は、その適用を排除して、諸般の事情を総合考慮して決定するものとされています。
職務発明対価の算定式は?
上記のとおりですので、現行特許法においても、職務発明対価に関する社内規定が、会社の利益や発明者の貢献度を度外視したような合理的ではないものである場合は、下記のような一般的で経済合理的な算定式によることとなります。
| 職務発明対価=独占の利益×発明者の貢献度 |
現行特許法35条5項では、「・・・その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。」とされています。
この「発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは、「その発明を自社の製品に実施して得られる利益」ではなく、「特許権の取得によりその発明を実施する権利を独占することによって得られる利益」すなわち「独占の利益」であると解されています。何だかおかしい感じがするのですが、そう解されています。
また、「使用者等が受けるべき利益」とは、既発生の利益に限定されず、今後、特許の有効期間満了までに生じると予想される「将来利益」も含むものと解されており、主張するストーリーによって大きく変動しますので、この点の弁護士の主張の巧拙により、結果は大きく変動することとなります。
例えば、普通にライセンスしているだけの場合はこの利益はライセンス収入のみになりますが、ライセンスしていない場合は 「特許権の独占権の効力として、他社が製品を取り扱うことができず独占したことによる利益」となりますので、非常に計算は難しいです。
仮に他社にライセンスしたと仮定して、その場合のライセンス料率を見積るしか方法は無いのですが、いくら巨額のライセンス料を貰ってもライセンスしたくなかったわけだからライセンスしていないのであって、計算が難しいことには変わりありません。また、クロスライセンスしてしまった場合、多くの場合、ライセンス料の支払いは存在しないため、何が独占の利益なのかさらに計算が無るかしくなります。
また、従業者等の貢献度についても、どのように判断すべきか合理的な計算方法など存在しませんので、ここもやはり、たんとする弁護士の主張の仕方の巧拙によりまた主張するストーリーの強さ弱さにより大きく結果が左右されます。
青色発光ダイオード裁判の際には、中村教授が「一人の天才によって発明された」と新聞広告を出したのに対し、会社側が「名もなき多数の技術者の総力によって開発された」と新聞広告を出していました。
職務発明対価の請求方法は?
会社との任意交渉で決着がつけば問題ないのですが、それで決着がつかなければ、訴訟をせざるを得ません。
訴訟の際には、職務発明対価の算定価格を証明しなければいけませんので、対象製品、会社の対象製品の売上・利益、対象製品のライセンス料、発明者の貢献度を裏付ける資料などが必要です。
また、時効は10年です。会社を退職されてから職務発明対価を請求されようとしている技術者様もいるかもしれませんが、時効にも留意する必要があります。
すなわち、職務発明対価の請求について、どのような手法を採用すべきか、どのようなストーリーを主張すべきか、どの程度の金額になるかなどについて、これらの諸般の事情を考慮して、検討することが重要です。