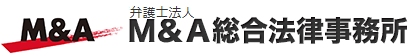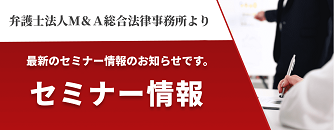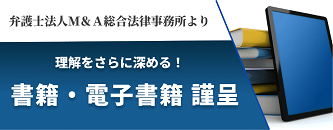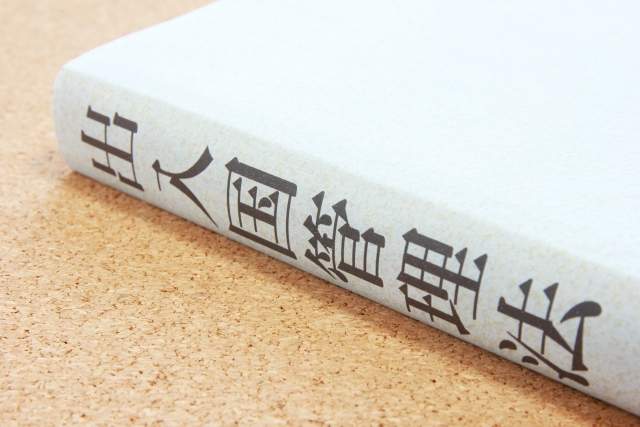契約社員を雇用している企業の場合、雇い止めによる損害賠償請求に注意しなければなりません。この記事では、契約社員の雇い止めの概要から、雇い止めが認められないケース、認められるケースについて解説します。
また、企業が契約社員を雇用する際にどういったことに気をつければならないのか、といった点についても取り上げているため、ぜひ参考にしてください。
⇒M&Aトラブルでお困りの方はこちら!
契約社員の雇い止めとは
契約社員の雇い止めとは、契約社員(期間を定めた労働契約を結んでいる従業員)の契約期間が終了したタイミングで、新たな更新を結ばず雇用を打ち切ることです。正社員は無期契約であり、契約更新が発生しないため、雇い止めされるといったことはありません。雇い止めは契約社員特有の事態だといえるでしょう。
なお、雇い止めはあくまでも新たな契約をしないことによる雇用の打切りであり、解雇には該当しません。
雇い止めの違法性
企業の中には、雇い止め=違法と考えている人もいるかもしれませんが、雇用契約において、どのくらい契約を結ぶかは基本的に当事者の自由です。
法律などに違反しておらず、企業と労働者の間で合意が得られていれば、雇用契約は成立します。そして、期間満了に伴う契約の終了も合法です。つまり、雇い止め自体は違法行為であるとはいえません。
雇い止めの制限
先述の通り、契約社員に対して、どのくらいの期間契約を結ぶか、どのタイミングで契約を打ち切るかは当事者の自由であるため、雇い止めは違法とはなりません。
しかし、企業と労働者の関係上、基本的には労働者がどうしても弱い立場におかれてしまうため、企業から雇用契約の打切りを強いられる可能性もゼロではありません。
そのため、このような事態を起こさないようにするために、「労働契約法」の第19条で、客観的合理性や社会通念上の相当性がない限りは、契約更新の拒絶を企業がわができないように定められています。
裁判になるケースも多い
雇い止めが原因となって、労働者と企業との間で裁判になるケースも少なくありません。万が一雇い止めが違法だと判断されてしまうと、雇い止めが無効になるのはもちろん、高額な損害賠償責任を課される可能性もあるでしょう。
実際に行われた裁判の中には、損害賠償の支払いが命じられているケースも少なくありません。例えば、航空会社が行った雇い止めに関する裁判では、約400万円が、レンタカー会社の裁判では約520万円が、さらに食品加工会社の裁判では約640万円の支払いが命じられています。
企業によっては、これらの損害賠償の支払い自体は大きなダメージにならないケースもあるでしょう。しかし、裁判によって違法性が認められたという事実は、金額的な損失以上に、社会的な評判や信頼を失うことになるため、結果的に大きな損害を被ることになります。
契約社員の雇い止め法理とは
先ほども触れているように、企業によって強制的な雇い止めが行われないように労働契約法第19条では、雇い止めに関する制限を定めています。これを雇い止め法理といいます。
ここでは、雇い止め法理がどのような時に適用されるのか、具体的な条件について解説します。契約社員との契約を打ち切る可能性のある企業の担当者は、どういったことをすると雇い止めの法理が適用されるのか、ぜひチェックしてください。
雇止め法理の適用場面
雇い止めの法理が適用される場面、つまり雇い止めが違法だと判断される際のポイントとしては、以下の2点が挙げられます。
- 契約社員との契約手続きがルーズであり、実質的に正社員と同様の雇用契約であると判断できる場合
- 契約社員が雇用契約が更新されることを期待してしまうのも無理のない状態である場合
1点目に関しては、例えば、契約更新の際に雇用契約書を企業側が作成していないケースや、作成はしているものの、できあがるのが契約更新を行った後になるケースなどが当てはまります。
このような状態だと、形のうえでは契約更新を行っていますが、書面で正式に行われたわけではないため、契約更新の存在しない正社員と同じだと見なされ、雇い止め法理が適用される可能性があります。
2点目に関しては、例えば、契約社員の仕事内容が一時的なものでなく、正社員と同じであると判断できるケースや、契約社員の雇い止めを長年に渡って社内で行なっていないケースなどが当てはまります。
このような場合、契約社員として働いている労働者は「ほかの正社員とやっていることは同じだし、社内で雇い止めもずっと行われていないし自分も契約更新してもらえるだろう」と考える可能性があるでしょう。このような場合においても、雇い止めの法理が適用される可能性があります。
この2点のどちらかに該当していて、なおかつ企業による雇い止めが「客観的に合理的な理由を欠いている」、「社会通念上相当であると認められない」と判断されると、労働者が契約更新を求めれば、企業は契約更新を強制されることとなります。
なお、ここでいう「客観的に合理的な理由を欠いている」、「社会通念上相当であると認められない」とは、世間的に見ても雇い止めになってもしょうがないと考えられるような事情が特にない、という意味だと考えてください。
⇒M&Aトラブルを解決する方法を見る!
雇い止めが認められる合理的な理由とは
雇い止め法理が適用される場面がある一方で、雇い止めが認められるケースもあります。雇い止めが認められるのは、合理的な理由がある場合です。ここでいう合理的な理由とは、正社員を解雇する際に必要となる解雇理由と同じものだと考えてください。
雇い止めのタイプ
企業が雇い止めを行う場合、その性質によって以下のタイプに分けることができます。
- 純粋有期契約タイプ
- 実質無期契約タイプ
- 反復更新タイプ
- 継続特約タイプ
ここでは、それぞれの雇い止めがどういったものなのか解説します。
純粋有期契約タイプ
純粋有期契約タイプとは、契約期間が満了した後に契約の打ち切りがあらかじめ予定されており、労働者が契約更新を期待することに対する合理性が認められないタイプのことです。
このタイプには一時的な仕事や季節限定で行われる仕事などが当てはまります。例えば、冬限定で行われるお歳暮関連の仕事や年賀状の仕分け業務、夏のみ行われる海水浴場関連の業務などが考えられるでしょう。
このような仕事は、世間一般から見ても、契約が更新される仕事であるとは考えにくいため、企業がわが雇い止めを行ったとしても有効であると認められると考えられます。
実質無期契約タイプ
実質無期契約タイプとは、形のうえでは契約社員ではあるものの、実質的には、契約期間の定めが特になく、無期契約と同じだと考えられるタイプです。
例えば、契約更新の手続きは行うものの形式的に行っているだけで、長期間の契約が反復して結ばれているケース、雇い止めを行った前例がほぼないケースなどはこのタイプに当てはまります。
このようなケースにおいては、労働者は「次回も契約が更新されるはず」と考えるため、企業側が雇い止めを行うと無効であると判断される可能性が高いでしょう。
反復更新タイプ
反復更新タイプとは、契約更新こそ複数回行われているものの、正社員と同等つまり無期契約と同じであると判断することはできないタイプのことです。
このタイプにおいては、正社員との仕事の内容の違いや過去に行われた雇い止めの前例は認められるケースが一般的となっています。この場合、雇い止めを有効であると認めたケースもありますが、必ずしも有効と判断されるわけではないため注意しなければなりません。
継続特約タイプ
継続特約タイプとは、雇用契約を結ぶ際に特別な事情や約束があったなど、労働者が契約更新に対する期待を持つことに対する合理性が認めらるタイプのことです。このタイプの場合、契約期間満了に伴う雇い止めを行ったとしても無効と判断されると考えられます。
このように、雇い止めを行うにしても、雇い止めに至るまでの背景によって、雇い止めが有効と判断されるケースもあれば、向こうとなるケースもあります。
これから雇い止めを行う可能性がある企業は、まず自社の雇い止めがどのタイプに当てはまりそうか検討しておくといいでしょう。
雇止めをする場合の手続き
雇い止めをする場合は、適切な手順に沿って手続きを行うことが大切です。例えば、以下のような契約社員の雇い止めを行うのであれば、雇い止めの30日前に予告しておかなければなりません。
- 1年を超えて雇用を継続している契約社員
- 3回以上更新した後に雇止めしようとしている契約社員
なお、上記の条件に当てはまっていても、事前に更新しないことを契約社員に対して伝えている場合は予告する必要はありません。具体的には、「3年契約で更新なし」である旨を雇用契約書に記載し、その点を踏まえたうえで採用しているケースなどが当てはまります。
予告が義務付けられているケースは限定的ですが、義務付けられていないケースであっても、トラブルを起こさないためにも雇い止めを行うと決めた時点で当該社員に対して伝えておくほうがいいでしょう。
雇い止めの予告をすれば、必ず雇止めが認められるわけではない
雇い止めの予告は、あくまでも最低限行うべき手続きの1つであり、予告したからといって必ずしも雇い止めが有効になるわけではありません。場合によっては雇い止め法理に触れ、無効となる可能性もあります。
⇒M&Aトラブルでお困りの方はこちら!
雇い止めによるトラブルを回避するポイント
雇い止めによるトラブルを避けるためには、契約社員の労務管理をしっかりと行うことが非常に重要です。ここでは、トラブル回避のポイントについて解説します。
書類作成は早めに行う
契約社員の契約更新を行うことになった場合、書類作成を後回しにすることは避けましょう。更新手続きを行うよりも前に必ず新しい雇用契約書を作成することで、雇い止め法理に触れる可能性が低くなります。
契約書は契約更新のたびに確認する
契約更新のたびに、雇用契約の内容は必ずチェックすることも忘れてはいけません。漫然と同じ契約内容で更新していると、実質的に無期契約と同じであると判断される可能性もあります。契約内容は、状況によっては契約社員本人と協議して決めるようにしてください。
契約社員の仕事内容をチェックする
企業によっては、契約社員と正社員の仕事内容がほとんど同じで、違いが明確になっていないケースもありますが、できるだけ違いははっきりとさせておきましょう。
例えば、契約社員に対しては、臨時的な仕事を行ってもらうようにすることで、正社員の仕事との違いが明らかになるため、雇い止めをした際に無効と判断される可能性が低くなると考えられます。
契約社員の契約更新に上限を設ける
契約社員の契約更新に年数の上限を設けることも、トラブル回避のポイントです。この場合、上限を設定したうえで、正社員登用の試験に合格すれば正社員になれる、といったルールをあわせて整備しておくことをおすすめします。
こうすることで、「試験に合格しないまま契約更新の上限がきたら雇い止めになる」と雇い止めの根拠を明確にすることができます。
雇い止めは早い段階で伝える
先ほども触れているように、雇い止めを行うことになった場合、早い段階で当該社員に対しては伝えておくようにしましょう。早めに伝えることで、契約社員は次の仕事を探す時間的な余裕を持てるためです。
また、雇い止めを伝える際は、ただ一方的に予告するのではなく、なぜ雇い止めになるのかできるだけ詳しく説明し、契約社員本人の納得を得られるように努力する必要があるでしょう。
まとめ
今回は、契約社員の雇い止めの概要から、雇い止め法理、雇い止めのタイプなどについて解説しました。雇い止めを行う場合は、雇い止め法理に抵触していないか確認したうえで、書類作成を早めに行う、早い段階で契約社員に予告するといった対応を取ることが大切です。一方的に契約を打ち切るだけでは、契約社員も不満に感じる可能性があります。
一定期間だけとはいえ、ともに働いた同僚であることに違いはないため、可能な限り丁寧な対応を心がけ、雇い止めの手続きを進めるようにしてください。