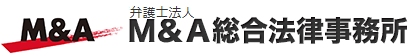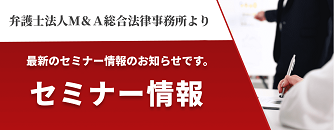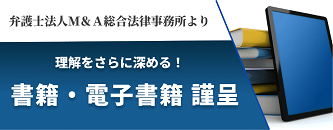会社側と従業員側との労使トラブルの内、よくあるケースが未払い残業代の請求です。
この未払い残業代の請求が裁判にまで発展しもしも敗訴するようなことがあれば、未払い残業代の他にも付加金や遅延損害金なども払わないといけなくなる可能性があります。
また、残業代を払わなかった会社として、良くないイメージもついてしまいます。
このようなことを避けるために、未払い残業代を請求された場合の反論方法を準備しておく必要があるのです。
今回は、未払い残業代を請求された場合にどうすれば良いのかを、実際の事例に基づき徹底解説していきます。
⇒問題社員にお困りの方はこちら!
営業職社員から残業代を請求された時の対応
営業職社員から残業代を請求されるケースは、社員が退職した場合に請求されることが多いです。
会社に在職しながら未払い残業代を請求することは、従業員にとっては難しいことなのかもしれません。
会社側は請求された時にまず一番始めにしなければならないことは、本当に請求された通りに残業代が発生しているのかを確認することです。
会社内に保管しているタイムカードやシフト表などの資料や記録などを調べる必要があります。
そうすれば、本当に残業したのかしていないのかを調べることができます。
会社としては、未払い残業代を払うにせよ反論するにせよ状況をしっかりと把握することが大切なのです。
残業代を払う必要がある場合
未払い残業代を請求された場合一番行ってはいけないことは、そのまま無視をすることです。
きちんとした話し合いをしないと、労働基準監督署に通報される恐れもあります。
また、労働組合から団体交渉を要求される可能もあります。
団体交渉は拒絶することができませんので、無視をし続けることはできません。
さらに、労働審判や労働訴訟まで発展していく可能性がありますので、無視をしないできちんと向き合いましょう。
未払い残業代を請求された後に調査してあきらかに未払い残業代を支払う必要性があった場合、反論しないで未払い残業代を払った方が良いです。
企業としては未払い残業代を払うとしてもできるだけ少ない金額を払う必要がありますので、まずは支払う残業代が法内残業なのか法外残業なのかをきちんと調べる必要があります。
法内残業と法外残業
残業代には、法内残業と法外残業の2種類があります。
法内残業とは所定労働時間を超えて働いてはいるが、1日8時間1週間に40時間の法定労働時間を越えていない残業のことです。
この場合、割増賃金はなく1倍で残業代を計算します。
ただし、法内残業であっても深夜労働であれば1.25倍、休日労働であれば1.35倍の割増賃金での計算になります。
また、法定労働時間を超えて残業する場合を法外残業といいます。
法外残業の割増賃金は、1.25倍で計算します。
従業員が未払い残業代を請求した場合、未払い残業代の他にも付加金や遅延損害金を払わなければならにケースがあります。
付加金
付加金とは労働基準法第114条規定された法律で、使用者が払わなければならない賃金を払わなかった場合にその金額と同一額の付加金を請求することができるとするものです。
使用者が払わなければならなかった賃金とは、以下になります。
- 解雇予告手当
- 使用者の責に帰すべき休業の場合の休業手当
- 時間外労働や法定休日労働に対する割増賃金
- 深夜労働に対する割増賃金
- 有給休暇中の賃金
即ち、従業員が未払い残業代を請求する時に、同一額の付加金を請求される可能性があるのです。
但し、実際には企業側が付加金を支払うケースはほとんどありません。
なぜなら、付加金の請求は労働審判では今まで命じられたことが一度もないため、裁判所での訴訟まで行われないと命じられることはないからです。
残業代の未払い請求はほとんどのケースが労働審判までで解決し、裁判所での訴訟まで行われるのは約20%と言われています。
付加金を払わないためにも、できるだけ早い解決を心掛ける必要があります。
遅延損害金
また、未払い残業代を支払いと同時に、遅延損害金の支払いをしなければならない可能性があります。
遅延損害金とは、民法上の規定による金銭債務の不履行のための損害賠償のことです。
遅延損害金は、在職中の分の請求は年利6%、退職後は年利14.6%の利息が付きます。
企業側が未払い残業代を実際に払った事例です。
光和商事事件
大阪地裁平成14年7月19日判決(労判833号22頁)
営業社員が勤務先の企業に対して、未払い残業代を請求した事例です。
企業側はこの従業員は営業社員のため、事業外労働基準法の38条の2第1項のみなし労働時間制により所定労働時間労働したとみなされるため未払い残業代は無いものと主張しました。
事業外労働基準法の38条の2第1項のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事した場合に使用者の指揮監督が及ばないため、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合があります。
そのような場合、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除して所定労働時間勤務したとみなす制度です。
しかし、この事例の場合の営業社員は毎朝出社して朝礼に出席して、その後外勤勤務に出た後午後6時までに帰社して事務所内の掃除をして終業としていました。
また、この事例の営業社員は、その日の行動内容を記載したメモ書き程度の予定表を使用者に提出していました。
さらに、企業側は、営業社員全員に会社所有の携帯電話を持たせていたため、営業社員の労働時間を算定することが困難とはいえないと判断されたのです。
その結果この営業社員は、労働基準法38条の2第1項の事業上外みなし労働時間制の適用を受けないと裁判所は判断しました。
⇒元従業員の未払い残業代でお困りの方はこちら!
未払い残業代を請求された場合
ここまでは、未払い残業代を請求された場合に企業が残業代を支払うケースを見てきました。
しかし、企業が未払い残業代を払わなくても良いような反論ポイントを探すことも大事です。
営業職社員の場合は、基本的には事業所の外で働いているので労働時間を算定するのは困難です。
しかし、営業職社員であっても、タイムカードなどにより残業時間を企業側が把握し、残業代を支払うことが原則になります。
但し、例外的に労働時間の管理が難しい場合には、以下で詳しく解説する事業場外みなし労働時間制を適用することができます。
ここからは、未払い残業代を請求された場合の反論ポイントについて見ていきます。
タイムカード以外の業務日誌などで確認をする
従業員に未払い残業代を請求されていても、タイムカードだけでは外出中にきちんと労働していたかどうかはわかりません。
営業職社員は直行直帰などでタイムカードを押していないケースも多く、請求された残業代が正しいかどうかの判断も難しいです。
そのため、タイムカードを押していない場合であっても業務日誌やメールの送受信記録やパソコンのログイン記録などを調査して、請求された残業代が正しいのかを判断する必要があります。
もし、タイムカードも押していなくてその他の記録などでも労働時間を判断できない場合に未払い残業代を請求されたら、裁判で敗訴する可能性が高くなります。
固定残業代制のため残業代は支払い済みの場合
定額残業代やみなし残業代として毎月定額の残業代を支払っている場合、企業側としては残業代を支払い済みであると主張できます。
固定残業代制とは、雇用契約書や就業規則に規定していれば違法ではありません。
但し、固定残業代制を採用したからといって、労働時間を管理しなくてもいいわけではありません。
決められた毎月の残業時間を超えて残業した場合は、残業代を払う必要があります。
一方、決められた毎月の残業時間に満たなかった月でも、決められた時間分の残業代は払わなければなりません。
そのため、固定残業代制を採用している企業で未払い残業代を請求された場合は、固定残業代制であることを雇用契約書や就業規則にきちんと記載されていることが大切です。
また、固定残業代制で定められた時間を超えた労働時間についても、きちんと割増賃金を支払っているかもポイントになります。
固定残業代制を採用している会社に未払い残業請求をしましたが企業側が勝訴した事例です。
富士運輸事件
東京高判平平成27年12月24日判決(労判1137号42頁)
ドライバとして働いていた元従業員が定額残業代に納得せずに、退職後に未払い残業代を請求した事例です。
この裁判は企業側が勝訴しましたが、その理由は以下の通りです。
この会社は、就業規則にきちんと定額残業代制について記載していたことと同時に、誰でも見れるように周知していました。
また、この会社は、実際の残業時間に相当する残業代よりも多くの金額を支給していました。
残業代が発生しない雇用形態であるため
従業員側は残業代が発生すると考えて未払い残業代の請求をしたとしても、みなし労働時間制だった場合は残業代は付きません。
みなし労働時間制とは、あらかじめ決められたした時間分働いたとみなす労働時間制度です。
みなし労働時間制には裁量労働制と事業場外みなし労働時間制があり、裁量労働制は専門業務型と企画業務型の2種類に分かれます。
専門業型裁量労働制とは研究開発など特定の業務を対象とした制度で、労使協定によってあらかじめ定められた時間労働したとみなされる制度です。
また、企画業務型裁量労働制とは企業で企画や立案や調査などの業務で働いている従業員に対する制度で、専門業型裁量労働制と同様に労使協定によってあらかじめ定められた時間労働したとみなされる制度です。
事業場外みなし労働時間制とは、事業場外で勤務する営業社員などの労働時間の把握が難しい場合に、1日何時間労働したとみなす制度になります。
この制度の場合は、実際の労働時間にかかわらず一定の労働時間働いたとみなされます。
そのため、実労働時間に応じた残業代を請求したとしても、認められることは難しいでしょう。
営業職社員から未払い残業代の請求を受けた時に、一つのポイントになるのが事業場外みなし労働時間制が適用されるかどうかです。
なぜなら、企業がみなし労働時間制を適用する場合、基本的には対象となる従業員への残業代の支払いは不要だからです。
そのため、企業側はみなし労働時間制が有効であると判断してもらう必要があります。
裁判所が事業場外みなし労働時間制を認めるかどうかは、就業時間の管理が難しい場合と判断できるかどうかがポイントになります。
反対に、営業職社員がタイムカードなどにより勤務時間の管理ができる場合は、就業時間の管理ができるため残業代を払わなければならない可能性が高いです。
また、事業場外みなし労働時間制が適用されていても、例外的に残業代を支払わなければいけないケースもあります。
まずは、深夜労働や休日労働の場合は、割増賃金が発生します。
他にも、業務を遂行するのに、通常に所定労働時間内に仕事が終わらない事情がある時なども残業代の支払いが発生します。
また、規定のみなし労働時間が10時間の場合など、法定労働時間の1日8時間を超えている場合は法定労働時間を超えた分は割増賃金を支払わなければなりません。
他にも、事業場外のみなし労働時間制は以下の場合は認められません。
- 従業員が一人での営業でなく複数でのグループ行動で活動していて、その中に労働時間の管理を行う人がいる場合
- 従業員が一人で営業していても、携帯電話などを利用して随時管理者の指示を受けながら営業する場合
- 会社などで訪問先や帰社時刻などの当日の具体的指示を管理者から受けた後、事業場外でその指示通りに動いた後帰社する場合
企業が事業場外みなし労働時間制を規定しているのに、事業場外みなし労働時間制は無効だとして割増賃金を要求し認められた事例です。
レイズ事件
東京地判平成22年10月27日判決(労判1021号39頁)
不動産販売会社の営業担当だった従業員が、指揮監督が可能であり労働時間の算定も可能であるため事業場外みなし労働時間制の適用は無効だとして割増賃金を請求した事例です。
この事例の場合は、以下の点により労働時間制の適用は無効だと判断されました。
労働者は原則として現場に直行して営業活動するのではなく、一度出社してから営業活動を行うのが通常でした。
また、出退勤においてタイムカードを押していたため、1日の労働時間の管理が可能でした。
さらに、この営業担当従業員の営業活動については、訪問する予定や帰社予定時刻などを会社に報告して営業活動中も状況などを携帯電話によって逐一報告をしていました。
このケースのように企業がいくらみなし労働時間制の規定をしていても、企業側の具体的な指揮監督が可能であり労働時間の算定も可能と判断された場合は事業場外みなし労働時間制の適用は受けないと判断されてしまいます。
⇒元従業員から不当解雇を言われお困りの方はこちら!
まとめ
営業職社員から未払い残業代を請求された場合、まずは会社内に保管しているタイムカードやシフト表などの資料や記録などを調査する必要があります。
事実をきちんと把握しないで、無視したり反論しらりすると、どんどんと問題が大きくなり裁判にまで発展して未払い残業代の他にも付加金や遅延損害金まで支払わなけらばならなくなる可能性もあります。
そのため、きちんと状況を把握して、反論する余地があるのかや、勝ち目があるのかを判断する必要があるのです。
その結果、あきらかに未払い残業代を支払う必要性があった場合は、反論をしないでできるだけ穏便に支払う金額を少なくすることを考えた方が良いでしょう。
反対に調査した結果反論ができそうな場合は、きちんとした反論をして未払い残業代を払わなくても済むように対処しましょう。
未払い残業代を請求された時の反論は以下になります。
- タイムカード以外の業務日誌などで確認をする。
- 固定残業代制のため残業代は支払い済みである。
- 事業場外みなし労働時間制などの残業代が発生しない雇用形態である。