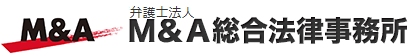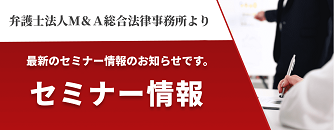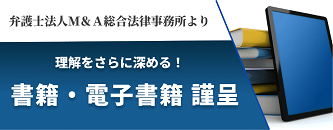会社に能力の欠如した問題社員がいる場合、経営側は会社の評判やお客様とのトラブルなどを考慮してなんとか辞めさせたいと考えるでしょう。
しかし、能力の欠如による解雇は、裁判で不当解雇と判断されて会社側が敗訴するケースも多々あります。
要するに、ただ能力が欠如しているだけで問題社員を辞めさせるのは難しい場合もあるということです。
それでは、どのような方法であれば問題社員を辞めさせることができるのでしょうか?
今回は、裁判に敗訴することなく問題社員を辞めさせる方法について詳しく解説していきます。
⇒従業員の横領・使い込みでお困りの方はこちら!
解雇とは
解雇とは、雇用主の側から雇用契約を一方的に解消することを言います。
もちろん、ただ「気に入らないから」や「仕事ができない」からといって簡単に解雇できるわけではありません。
解雇をするには、それなりの理由がないといけません。
労働基準法における解雇
労働基準法では、どんな解雇事由であったなら解雇されることがあるかを就業規則と労働契約書に明示しなければならないことになっています。
また、解雇をするには、就業規則と労働契約書に明示された要件と合致しなければなりません。
この労働基準法の要件は、平成16年1月からの法改正により新たに設けられたものです。
そのため、就業規則に具体的な解雇の要件を記載していない会社も多くあります。
法改正以前から就業規則を見直していない会社は、従業員を解雇する時にトラブルにならないように見直しておく必要があります。
ただし、いくら就業規則や労働契約書に明示されていても、合理的な理由が無ければ解雇をすることはできません。
なぜなら、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と労働契約法第16条にあるからです。
それでは、従業員を解雇するための客観的に合理的な理由とはどのようなものなのでしょうか?
労働契約法第16条では、客観的に合理的な理由が社会通念上相当であると認められなければいけません。
認められるかどうかはケースバイケースですが、以下の事由が考えられます。
会社の解散や倒産など
会社が解散や倒産などで無くなってしまう場合は、ほとんどが客観的に合理的な理由になり得ます。
従業員の勤怠が悪い
多少の遅刻や休暇だけでは、客観的に合理的な理由にはならない可能性が高いです。
また、会社が従業員の勤怠が悪いことに対して、指導や注意をきちんとしていたかも重要なポイントになります。
従業員の能力が不足している
仕事のキャリアが短かったり、会社側がきちんと能力が高くなるための教育をしていたかどうかが大きなポイントになります。
ただ能力が不足しているから解雇では、社会通念上相当とは言えない可能性があるのです。
従業員の勤務態度が悪かったり、秩序に違反した場合
勤務態度についても、会社側が指導や注意をきちんとしていたかがポイントになります。
ただ態度が悪いからといって、辞めさせることは難しいです。
会社秩序に違反した場合は、その結果どのような被害を受けたかやトラブルの程度などが重要です。
解雇予告
労働基準法では解雇を行う時は、解雇をしようとしている従業員に対して30日前までに解雇の予告をする必要があります。
解雇予告は書面で行う必要はありませんが、後々のトラブルの原因にならないように解雇理由が記載された「解雇通知書」を渡すのが良いでしょう。
ただし、従業員側から書面での授受を要求された場合は、解雇理由を記載した書面を渡さなければなりません。
一方、解雇予告を行わないで従業員を解雇するには、最低でも30日分の平均賃金を支払う必要があり、これを解雇予告手当と言います。
即時に従業員を解雇する場合は、平均賃金の30日以上分の解雇予告手当を支払わなければなりません。
また、従業員を解雇しようとする日まで30日に満たない場合は、解雇予告をした上で不足している日数以上分の解雇予告手当を支払う必要があります。
例えば、解雇をしようとする日が20日後の場合、解雇予告をした上で平均賃金の10日以上分の解雇予告手当を支払う必要があるのです。
解雇予告が不要なケース
このように、従業員を解雇するには基本的には解雇予告をしなければなりませんが、例外的に事前に労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受ければ解雇予告が不要なケースもあります。
- 従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合
- 天災地変等により事業の継続が不可能となった場合
上記の場合は、解雇予告や解雇予告を支払わなくても即時に解雇をすることができます。
また、試用期間中の従業員、4ヶ月以内の季節労働者、契約期間が2ヶ月以内の従業員、日雇労働者に関しては、解雇予告が適用されません。
しかし、以下の期間を越えて引き続き雇用された後に解雇をする場合は、解雇予告が必要です。
| 試用期間中の従業員 | 14日間 |
| 4ヶ月以内の季節労働者 | その契約期間 |
| 契約期間が2ヶ月以内の従業員 | その契約期間 |
| 日雇労働者 | 1ヶ月 |
解雇をする前に考慮しなければいけないこと
問題社員を解雇しようとした時に、場合によってはトラブルに発展することも考えられます。
また、トラブルから裁判にまで発展して最終的に不当解雇ということになれば、会社は多額のお金を支払わなくてはいけない可能性もあります。
このようなリスクを回避しながら問題社員を辞めさせるためには、解雇をする前にいろいろなことを考慮しなければなりません。
ここでは、問題社員の解雇をする前に考慮しなければいけないことについて解説していきます。
従業員の能力が不足しているため解雇する場合
会社が従業員の能力が上がるような教育を行ったのかが争点になります。
そのため、会社が従業員に対して十分な教育や指導をしたという記録などを残しておく必要があります。
要するに、会社はきちんと教育をしたにもかかわらず、能力が不足していて会社に損害を与えたことを主張できるものを残しておく必要があるのです。
また、能力が不足している従業員の適性を見極め他の部署への配置転換を行うなど、適性を試す行為を行ったかどうかも重要になります。
雇用期間がまだ短い状態での解雇の場合
採用してからすぐに問題をおこすような社員には、会社もすぐに解雇を行いたいでしょう。
しかし、就業期間が短い場合の解雇は、会社側の十分な指導や教育ができていないと判断される可能性が高いです。
さらに、成長の機会も与えていないと判断され、裁判になれば不当解雇と判断される可能性もあります。
そのため、雇用期間が短い状況での解雇は、間違いなく正当な解雇と認められるような事由が無い限りは止めておいた方が良いです。
特に、試用期間を設定している場合の解雇は、適性を見る期間の解雇であり会社側が裁判で負けた判例も多いため避けた方が良いでしょう。
このように、解雇を行う前にはトラブルになって裁判になる可能性があることまで考慮する必要があります。
しかし、不当解雇と判断されないための十分な準備を行ったとしても、裁判のプロではないため準備が不十分なこともあります。
また、考えもつかなかった理由で不当解雇と判断されてしまう場合もあるかもしれません。
そのため、解雇を行う前には、弁護士などの専門家に相談することを検討するのも良いでしょう。
⇒従業員の着服・不正行為の問題を解決する方法を見る!
退職勧告
問題社員を辞めさせる方法として、解雇ではなく退職勧告という方法もあります。
解雇とは会社側が一方的に従業員を退職させる方法ですが、会社側が従業員に対して退職を促すことを言います。
即ち、退職勧告とは会社側から退職は働きかけますが、あくまでも従業員側が了承して同意の上で退職届けを提出してもらう方法です。
このように、退職勧告は従業員の同意の上行われるのでトラブルが少なくなりそうですが、そうでもありません。
従業員側から見れば、退職を強要されたので解雇と同じことと考える場合があります。
実際に裁判になり会社側が敗訴し、慰謝料などを払わなければならなくなる可能性もあります。
しかし、一般的にはいきなり解雇をする前に退職勧告をすることで会社側のリスクを減らすことができますし、穏便に解決できる可能性も高いです。
ここでは、退職勧告について解説すると共に、問題社員を退職勧告にて辞めさせる方法についても詳しく解説していきます。
問題社員を辞めさせる方法として、退職勧告を選ぶこと自体はまったく違法ではありません。
むしろ、一方的に解雇をするよりもきちんと従業員と同意がとれる分だけトラブルの可能性も低くなります。
しかし、解雇に近いような形や無理矢理に合意をさせて退職願を提出させると、後々トラブルになり不当な退職と判断され従業員の退職の無効と慰謝料を払うことになりかねません。
そのため、きちんと合意できるような退職勧告ができるように注意する必要があります。
退職勧告で慰謝料などを払わないようにするための注意点
退職勧告をした場合、後でトラブルにならないようにするための注意点は以下になります。
「自主退職しなければ解雇する」といって辞めさせることはしてはいけません。
解雇よりも自主退職の方が従業員に傷がつかないことを餌に無理矢理辞めさせると、後からトラブルになった場合に不利になる可能性があります。
退職勧告に応じてもらうために、配置転換や敢えて作業を振らない状態にしてはいけません。
また、退職をしなければ給料をカットするなど脅かしてもいけません。
従業員が退職勧告に応じるしかない状況に追い込んだ場合も、後からトラブルになった場合に多額の慰謝料などを払わなければならなくなる可能性があります。
退職に応じるまで何回も退職勧告をすると、当たり前ですが退職強要になります。
そして、トラブルが大きくなり裁判になった場合は、敗訴の可能性が高くなります。
会社としては退職勧告をしても雇用保険上の自主都合退職として扱いたいと考えますが、後々のトラブルを防ぐためにも会社都合退職として扱った方が良いでしょう。
自己都合退職と会社都合退職では退職金にも差がでる会社が多いと思いますので、トラブルになりやすいです。
また、退職時期も会社が決めたようにすると、退職強要として判断される場合があります。
さらに、退職勧告は違法ではないのですが、うつ病を理由に退職勧告することは違法になる場合がありますので注意が必要です。
解雇の種類と解雇の方法
能力が不足しているような問題社員を会社が辞めさせようとする場合、まずは退職勧告をすると良いでしょう。
しかし、退職勧告をしても辞めることを拒否された場合、会社側は次に従業員に対して解雇予告を行います。
このような、能力が不足しているような問題社員に行う解雇は普通解雇と呼ばれています。
このように解雇には程度や状況によって、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3種類に分かれます。
以下は3種類の解雇についての説明です。
普通解雇
労働契約の継続が困難な事情があるときに行われる解雇で整理解雇、懲戒解雇以外の解雇のことです。
例えば、勤務成績が異常に悪く指導を行っても改善されない場合や、健康上の理由で長期休暇を取得していて回復の見込みがない時や、協調性に欠けることで業務に支障を生じ指導をしても改善されない時などが考えられます。
整理解雇
会社の経営悪化のため解雇により人員整理を行うことです。
整理解雇を行うには以下の4項目をすべて満たす必要があります。
- 整理解雇することに客観的な必要があること
- 解雇を回避するために最大限の努力を行ったこと
- 解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的に行われていること
- 労使間で十分に協議を行ったこと
懲戒解雇
極めて悪質な規律違反や非行などを従業員が行った場合、懲戒処分として行われる解雇です。
懲戒になる具体的事由を就業規則や労働契約書に明示しておく必要があります。
普通解雇と懲戒解雇の違いについて
解雇の種類の内、整理解雇は会社の業績悪化のための解雇ですが、普通解雇と懲戒解雇については違いがわかりづらいです。
ここでは、普通解雇と懲戒解雇の違いについて解説していきます。
解雇事由の違い
普通解雇と懲戒解雇の違いは会社ごとに違っていて、就業規則に定められます。
一般的には懲戒解雇の解雇事由は規律違反などを行った場合で、普通解雇の解雇事由は従業員の能力不足などです。
一般的な懲戒解雇の事由の例
- 横領などの不正行為
- 業務命令の拒否
- 長期の無断欠勤
- セクハラやパワハラ
- 経歴詐称など
一般的な普通解雇の事由の例
- 病気やけがのための長期の欠勤
- 能力不足や成績不良
- 協調性が欠如している
- 業務命令の違反など
解雇予告が必要かどうかの違い
普通解雇は解雇予告か解雇予告手当の支払いが必要だが、懲戒解雇は労働基準監督署の除外認定を受ければ解雇予告か解雇予告手当の支払いが不要のケースがあります。
労働基準監督署の除外認定の対象となるケースは以下になります。
- 原則としてきわめて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合。
- 賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合。
- 雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入の際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合。
- 他の事業場へ転職した場合。
- 原則2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。
- 出勤不良又は出欠常ならず、数回に亘って注意を受けても改めない場合。
退職金が支給されるかどうかの違い
退職金は就業規則の退職金規定に定められている会社が多いですが、普通解雇の場合は基本的に退職金は規定通りに支給されるのが原則です。
一方、懲戒解雇は、整理解雇退職金を減額したり支給しないことを退職金規定に記載している会社が多いです。
⇒従業員が問題社員なので徹底的に対応したい場合はこちら!
解雇をする会社側のリスク
会社が問題社員を解雇する場合の最大のリスクは、不当解雇と判断されることです。
訴えられて不当解雇と判断された場合、損害賠償や慰謝料を払わなければならないかもしれません。
解雇に対する損害賠償は、多額になり会社にとってのリスクは相当なものです。
そのため、不当解雇と判断される可能性があるような事象であれば、解雇は止めた方がいいかもしれません。
ここでは、解雇に関する事例を挙げて、どのようなリスクがあるかを解説していきます。
能力不足による解雇が不当解雇と判断された判例
森下仁丹事件
大阪地裁平成14年3月22日判決(労働判例832号76頁)
医療品の製造販売会社の販売従業員を解雇した事例です。
従業員が成績不振というだけで、他の職種に配置転換を検討したり、解雇ではなく降格などの検討をするべきと判断されました。
技能発達の見込みがないとして解雇をしなければならないほどではないとの判断で、解雇が無効となりました。
約600万円の支払いを命令されています。
セガ・エンタープライズ事件
東京地裁平成14年3月22日判決(労働判例770号34頁)
1年間の人事考課平均値が3点台である従業員に対し、就業規則に定められた解雇事由である「労働能率が劣り、向上の見込みがないと認めたとき」に当たるとして解雇。
しかし、判決では人事考課の低さだけでは上記解雇事由には該当しないとしました。
さらに、会社が教育や指導や配転措置などを行っていないとして解雇を無効とした事例です。
休職期間満了による解雇が不当解雇と判断された判例
東芝事件
会社の休職制度に従って休職をしていたうつ病になった東芝の技術職の従業員が、休職期間満了で解雇になりました。
この解雇に対して従業員は、うつ病は業務上の疾病であることから解雇は無効として地位確認と解雇後の未払賃金と損害賠償を求めて提訴。
そして、一審(東京地裁平成20年4月22日判決(労働判例965号5頁))、二審(東京高裁平成23年2月23日判決(労働判例1022号5頁))共に解雇は無効として従業員の主張を認めたのです。
その判決を不服とした東芝側が上告をし、最高裁判所(最高裁二小平成26年3月24日判決(労判1094号22頁))はその主張を認め東芝側の敗訴部分を破棄しました。
そして、傷病手当金、休業補償給付などの損益相殺の範囲についても違法であるとして、東京高裁に損害額について審理させるため差し戻したのです。
東京高裁の差戻審(東京高裁平成28年8月31日判決)では、休業損害が発生した時点での損益相殺を認めず1,600万円余りの遅延損害金が認容されました。
また、慰謝料額については160万円を認める判断をしたのです。
円満に問題社員を辞めさせる方法(まとめ)
問題社員を辞めさせるためには、辞めさせた後にトラブルになって会社が損害を負うことを避けなければなりません。
そのため、十分な準備をしておくことが重要なポイントです。
まずは、会社が従業員を解雇する場合の条件について、就業規則と労働契約書に明示しておくことが大切です。
次に不当解雇と判断されないため、会社側としても十分な指導や教育をしておくことや、適性にあった配置転換を行うなどをしておく必要があります。
そして、不当解雇と絶対に判断されない事由でない限りいきなり解雇を行うのではなく、まずは退職勧告を行いきちんと従業員と合意をとっておくことが大切です。